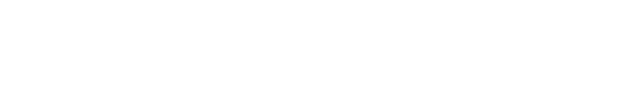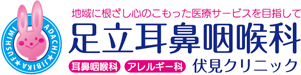マイナンバーカードについて

マイナンバーカードを用いた資格確認の事を「オンライン資格確認」と呼びます。国の新しい制度で医療機関は原則義務化しております。
この制度、マイナンバーカードを持参した場合と忘れた場合で患者さんの窓口負担にも影響してきます。少々わかりづらいと思いますので、当ページでご説明致します。
マイナンバーカードを使わないデメリット
最初に一番お伝えしておきたいことをお話します。
それは・・・マイナンバーカードを従来の保険証代わりに使わないと、窓口負担金が高くなる!
さらに・・・診療情報の提供に同意しなくても、同様に高くなる!
そして・・・カードが破損していたりして使えない場合も高くなる!
「え、そんなの聞いてないよ!本人の自由なんじゃないの?」
最初に申し上げたように、医療機関は4月からオンライン資格確認が原則義務化されています。語弊がありますが、簡単にいえば強制的に使わされるということです。そうでないと支払うお金がわずかではありますが、高くなるという仕組みになりました。
金額的には3割負担で約10円~20円程度ですが、初診時と再診時でも変わってきます。医療機関を受診する場合は、マイナンバーカードを持参して頂くのが無難だと考えます。
マイナンバーカードと健康保険証情報について
すでにお持ちの方は結構多いのではと思いますが、医療機関でマイナンバーカードを使うには「健康保険証」と紐づけないと使用出来ません。大丈夫という方は結構ですが、この点は今一度ご確認頂く必要があります。
また国の医療情報サーバーとつながりますので、過去の医療情報を確認出来ます。病歴やお薬の情報などのチェックがより厳密に出来る仕組みになっています。
今までの健康保険証と違うところ
今までは保険証は月に1回持参頂ければ結構でしたが、マイナンバーカードに関しては毎回必ずお持ち下さい。そうでないと負担金が高くなります。
従来は月に1回確認していれば大丈夫でしたが、正式には毎回持参がルールでした。実際月の途中で保険証が変わることもありますので、今後は毎回持参するようにという厚生労働省の指示になっています。
読み取り機の操作方法
今までお話してきたように、原則マイナンバーカードで受付をして頂くようになります。
- 受付の前に、マイナンバーカードの読み取り機を設置してあります
- ご自身でマイナンバーカードを読み取り機に差し込んで頂きます
- 顔認証か暗証番号入力どちらかで、本人確認する
- 診療情報の提供に同意するかしないかをタッチする
- カードをお取り下さい